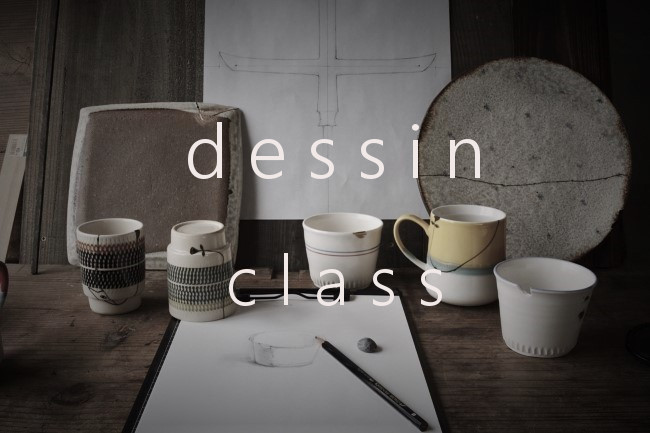これって金継ぎコンテンツとしてはあまり必要ないんじゃない?
…うっ…そ、そんなことないさ。—と信じて「スパチュラ・シリーズ 第三弾」ページ、発行致します。
ぜひ、役立たせてください。お願いします。
今回はより「実践的なヘラの使い方」です。
基本テク
まずは「練り」の時の基本的なヘラの動き方です。

箆の持ち方、よろしいでしょうか?
え?何それ??という方は、こちらを参照してください
▸ 箆の持ち方・動かし方 Part 02 〈持ち方・回し方〉編
この説明画像では「水練り砥の粉」を使っています。
錆漆、麦漆、刻苧漆、生漆の精製…などなど、基本的にはここで説明する箆の動かし方と一緒です。

砥の粉の下を滑り込ませるように入れていきます。

砥の粉を持ち上げるように箆を手前に回転させながら、
箆の上に置いてある人差し指をスライドさせます。

箆は手前に回転。
人差し指は箆の向こう側にスライド。

箆を手前にパタンと倒していきます。


「パタン」と倒れました。
人差し指はスライドさせていたので、いつの間にか再び箆の上に置いてあります◎

砥の粉を上から押さえつけつつ、潰しながらヘラを手前に引いていきます。

これが基本的なヘラ動作です。
よろしいでしょうか?わかりづらいですね~。
次はもうちょっと実践的にやってみます。
実践 その1
引き続き使っているのは水練り砥の粉です。
みなさんも練習する時はこれでやるのがいいかと思います◎

箆の角度が鋭角になるように持って、砥の粉の下に滑り込ませていきます。
ちなみにヘラの頭の分部で、鋭角の箇所が「箆先」、鈍角の箇所が「箆尻」と呼びます。

砥の粉の下に入れつつ箆を「向こう側」にスライドさせていきます。
巻き込んでいく感じです。

持ち手部分を向こう側に送りつつ、箆を回転させていきます。
箆尻を軸にして箆を手前に返していきます。

箆をひっくり返しつつ、持ち手の方は徐々に持ち上げていきます。

箆がひっくり返りました。
今度は砥の粉を下へ押し潰しながら箆を手前に引いていきます。
持ち手を下方向に動かしつつ手前に引きます。

砥の粉、潰れます。

手前にビーっと引いていきます。

はい、こんな感じです◎
どでしょうか?できましたでしょうか??
今度は反対方向の実践的ローリング・テクを解説します。

同じく、箆を砥の粉に下に滑り込ませていきます。
と同時に、持ち手を画面左側にスライドさせていきます。
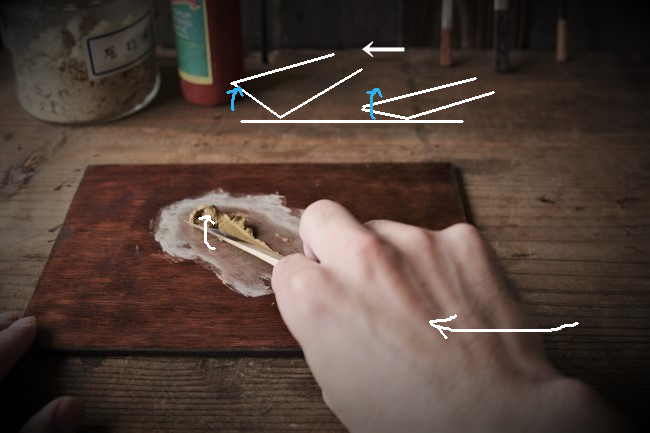
箆尻を軸に箆先を返していきます。
持ち手は左側にスライド。
巻き込んでいく感じです。

箆を返しつつ、持ち手を上げていきます。

箆がひっくり返りました。

手前に箆を引きつつ、砥の粉を下に潰していきます。
同時に、持ち手も下げていきます。

手前に引きます。
これが基本的なヘラ動作になります。
この2つの動作を繰り返しながら「ネタ」を練っていきます。
実践 その2
カメラ・アングルを変えた解説です。

箆先が手前にある場合の箆の動かし方です。ご注意ください。

「ネタ」の下に箆を滑り込ませます。

巻き込む感じで、箆と持ち手を徐々に手前にスライドさせていきます。

箆尻を軸に箆を返していきます。
持ち手はさらに手前にスライドさせていきます。

箆を返しながら持ち手を上げていきます。


箆が返りました。

砥の粉を潰すように箆を下方向に移動させつつ、持ち手の方も手前下方向に動かしていきます。

手前に引いていきます。
どうでしょうか?何となく分かったでしょうか?相変わらず鳩屋の説明は分かりづらいでしょうか??
引き続き、もう一ページくらい「実践編」を追加しようと思います。
次回もお楽しみに!(楽しくないかしら?)